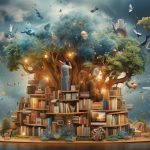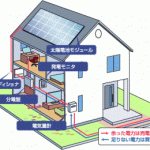最終更新日 2025年7月24日 by anagra
海外旅行といえば、世界中から観光客が集まる定番スポットを思い浮かべる方が多いかもしれません。
でもここ数年、日本の神社に憧れて来日する外国人観光客が増えているってご存じでしたか。
私自身、大阪の広告代理店でデジタルマーケティングを担当していたとき、外国人が神道文化に強い興味を持っている事例を何度も目にしました。
神社本庁という言葉を耳にすると、
「なんだか敷居が高そう…」
「伝統的だけど海外に伝わるの?」
といったイメージを持つ人もいるかもしれません。
そこで本記事では、神社本庁とインバウンド需要の関わりにフォーカスしながら、SNSを活用したPR戦略についてご紹介していきます。
最新の事例や私が広告代理店時代に手掛けたキャンペーンの経験を交えつつ、「神道文化×SNSマーケティング」の可能性を一緒に探っていきましょう。
目次
神社本庁とインバウンドPRの基礎知識
神社本庁の役割とは?
神社本庁とは、日本全国にあるおよそ8万社といわれる神社を包括する、神道界で最大規模の組織です。
神道文化の保存・振興を担いつつ、各神社の活動をサポートする役割を果たしているのが大きな特徴。
ただ、若い世代や海外の方にとっては「神社本庁」という名前がピンとこない場合も少なくありません。
「神社=観光スポット」というイメージはあっても、その背後にある組織や歴史的背景にはあまり注目が集まらないからです。
しかし実は、国際的な行事や外交のシーンで神道文化が紹介されることも増え、神社本庁にも海外から問い合わせが寄せられるようになっています。
インバウンド需要の高まりと神社の魅力
日本を訪れる外国人観光客が増加するなか、神社は重要な観光資源として見直されています。
鳥居の荘厳な雰囲気、御朱印の芸術的なデザイン、伝統行事の非日常感など、魅力は挙げ出すとキリがありません。
特に近年は、SNSで写真や動画をシェアすることを目的に旅先を探す人が増加。
「ここでしか体験できない!」という独特の文化や儀式、限定の御朱印などが拡散され、自然と神社巡りに興味を持つ外国人が増えています。
この波に乗って、神社本庁全体としてもインバウンドPRを強化しようという流れが加速しているわけです。
SNS戦略の重要性:神社本庁が果たす役割
効果的なSNS活用のポイント
私は大学時代から、神社の広報活動にSNSを活用できるかどうかを調べてきました。
当時はまだInstagramも今ほど普及していませんでしたが、今や写真・動画が主役の時代になっています。
神社本庁が各神社と連携してSNSを発信する際、ポイントになるのは「わかりやすいビジュアル」と「物語性のある投稿」です。
- ビジュアル重視
鳥居や本殿といった神社のシンボルを、外国人でも直感的に“美しい”と感じられる写真で表現すると、拡散力が高まります。 - ストーリーテリング
神社の歴史や祭神の由来を簡潔にまとめ、あわせて身近な物語として伝えることで投稿への興味を喚起します。
たとえばTwitterでは文字情報を活かした短文ストーリーを展開し、Instagramでは美しい写真や短尺動画で情緒的に伝える、という形で使い分けると効果的です。
神社運営視点から見るPR戦略
神道文化には、神聖性と伝統が何よりも重んじられる側面があります。
そのため、運営者の中には「派手なSNSプロモーションは神聖性を損なわないか」と懸念する声も。
一方で、若い世代を中心に「SNSで知って初めて神社へ興味を持った」という声も続出しているのが現状です。
このバランスを保ちながら情報発信するには、神社本庁として「正確な神道の知識や行事の意義」を発信しつつ、「写真映え・動画映えする要素」も発掘していく必要があります。
祭礼や行事の様子をライブ配信するとき、神職の許可を得ること、神社の儀式の神聖性をしっかり説明することなど、運営者側の視点を大切にしながら魅力を伝えるのが理想です。
事例研究:成功するインバウンドPRとSNS連携
地方神社のSNSキャンペーン成功例
私が広告代理店時代に印象的だったのは、ある地方神社のSNSキャンペーンです。
観光客が減少していた地元の神社に対し、海外向けの短期集中プロモーションを提案しました。
そのとき重視したのは「地元住民を巻き込み、地域の風土とセットで神社の魅力を発信する」こと。
結果的に、外国人観光客だけでなく「こんなに素敵な場所があるとは知らなかった」と地元の若者も足を運んでくれるようになり、キャンペーン期間終了後もSNSを通じた情報発信が継続していきました。
神社本庁が取り組む最新事例
神社本庁としても、オンラインでの御朱印授与やライブ配信などの取り組みが始まっています。
遠方でなかなか足を運べない人や、海外在住の方にも神社の文化を知ってもらうための工夫として注目度が高いです。
例えば、以下のような新しい動きが見受けられます。
# オンライン限定御朱印の例
- 事前予約をオンラインで受付
- 御朱印帳に神職が手書きしたものを郵送
- イベント期間限定のスタンプやデザインを導入
上記はあくまで一例ですが、伝統的な御朱印文化とオンライン施策が融合する面白い事例といえます。
神社本庁がこういった先進的な取り組みを後押しすることで、全国の神社が次々と新しいチャレンジを行いやすい環境が整ってきているのです。
海外へのアプローチ:SNS以外のデジタル施策
多言語対応とコンテンツ最適化
海外の方に神道文化を正しく理解してもらうには、多言語化が欠かせません。
SNS投稿だけでなく、神社のWebサイトやオンライン予約フォームなども英語・中国語・韓国語を中心に対応を進める必要があります。
最近はAI翻訳ツールが発達しているため、基本的な翻訳であればコストを抑えつつ素早く実装できるようになりました。
ただし一部の神道用語は機械翻訳が苦手としているので、専門家の監修も欠かさないようにするのが望ましいところです。
また、InstagramやYouTubeに合わせた縦型動画コンテンツの制作、スマホでの閲覧を前提としたページデザインなど、プラットフォームに最適化されたコンテンツ作りも重要です。
口コミとレビューサイトへの誘導
SNSだけでなく、トリップアドバイザーやGoogleマップなどのレビューサイトも欠かせない存在になっています。
訪日観光客の多くは、実際の体験談を重視して次の旅先を決めるからです。
ここで大切なのは、ポジティブな口コミに加えてネガティブな意見にも真摯に対応すること。
たとえば「参拝作法がわからなかった」「英語の案内が少ない」といった声があれば、現場で案内板を追加したり、公式SNSで参拝方法をわかりやすく紹介したりといった改善につなげられます。
こうした取り組みが重なると、自然と「日本の神社文化は丁寧でフレンドリー」という印象が海外ユーザーの間に広まりやすくなるのです。
SNS運用とレビューサイト対応の比較表
以下はSNSとレビューサイト、それぞれの運用上の特徴をまとめたものです。
使い分けのヒントとして参考にしてみてください。
| 特徴 | SNS (Twitter/Instagram等) | レビューサイト (TripAdvisor/Google等) |
|---|---|---|
| 拡散力 | 高い (特にリツイートやハッシュタグで拡散しやすい) | 低い (検索やレコメンドが主だが、定着性は高い) |
| 信頼度 | 比較的低め (公式情報としては認識されにくい) | 高め (実際の訪問者の声なので説得力がある) |
| コミュニケーション | リアルタイム (コメント欄やDMで即やり取りが可能) | 遅め (レビュー投稿への返信は可能だがタイムラグが生じる) |
| 主な目的 | ファン獲得・話題作り・タイムリーな情報発信 | 信頼構築・訪問検討者向け情報提供 |
まとめ
こうして振り返ると、神社本庁が担う国際的なPR戦略は、まさに今が大きな転換期といえるでしょう。
29歳の私から見ても、SNSやデジタルツールを活用すれば、神社文化の「厳かさ」を保ちながら世界中の人々とつながれる可能性がぐんと広がると感じています。
インバウンドPRにおいては、ビジュアルを活かせるInstagramや短い言葉で拡散力を高められるTwitter、レビューサイトでの実体験共有など、さまざまなチャンネルをバランス良く使うことが鍵。
神道文化の深みをきちんと伝えつつ、SNS映えやライブ配信といった今どきのアプローチも取り入れることで、より多くの人に神社の魅力が届くはずです。
伝統とデジタルを橋渡しする新たな広報手法が、全国の神社を舞台にどんどん生まれていく未来。
これからも私自身、神社巡りをしながら「神社本庁×SNS」の可能性を探求し続けたいと思います。
皆さんもぜひ、近くの神社やお気に入りの神社をSNSでチェックして、新しい発見を楽しんでみてくださいね。